「うん、そうだね。それできみはどうしたの?ユリ」 暇な時間を見つけたので、委員会の仕事を少しでも少なくしといてやるかと用具倉庫に向かって歩いていたら聞きなれた声が聞こえてふと立ち止まった。用具倉庫からそう遠く離れていない場所にある茂みの中から、同期のくのいちであるの声が聞こえたのだ。はくのいちの中ではわりと仲がいい方で、会えば挨拶をして立ち話もするし、一緒に食事を取ったことさえあった。忍たまとくのいちは1年の頃は敵対同士であるといっても過言ではない関係なのだが、それは1年のときの話。6年生にもなればお互い丸くなり、敵対するときはもちろんあるが友好関係を築いている生徒も少なくはないのだ。 俺とそんな関係であるがなにやらコソコソと話をしているという時点でまず興味を持ったのだが、耳を澄ませていると幼い女子の嗚咽が聞こえてきて、一体何の話をしているのかと一層好奇心をそそられる。そのまま声が聞こえる茂みから少し離れて耳を澄ませていると、聞き取りづらくはあるが嗚咽を零しながら幼い女子がなにか言っているのが聞こえた。 「ど、どうしよ…って、おも、ちゃって、そのまま…たたいちゃ、ったん、です、ぅ、わあぁぁん!」 どうやら喧嘩の相談を受けているようだ。これは忍たまでも同じであるが、くのいちの最上級生であるはこういった私情の悩み事を相談される立場にあるのだろう。それにしても叩いた、とは。が話している相手が分からないので断定はできないのだが、おそらくくのいちの1年生か2年生だろう。忍たま内なら頷けるが、かわいい女子が多いくのいち内でもそのような過激な喧嘩が起こっているのだと思うとなんとも女子とは恐ろしいものだ。人は見かけによらずとはよくいったものだ、と一人で思っていると、はもっと大声で泣き出した下級生をなぐさめながらもゆっくりと話しはじめた。 「ユリは焦ってしまったんだよね。そうだよね?」 「は、はい…」 「だから、叩くつもりは全くなかったのに、相手を叩いてしまった。それがどういうことかは、分かる?」 「…い、いけないこと…です…。わたしが、わるいのです」 「それが分かっているなら大丈夫。仲直りの方法は、知っているでしょ?」 「は、はい…。でもっ、先輩、なかなおり、してくれるでしょうか…。き、きっとわたしは、嫌われちゃったと、おもいます」 「大丈夫だよ。きみたちはこれから6年間も一緒の場所で過ごすんだ…きっと、仲良くなれるさ」 「ほんとうでしょうか?」 「私と仲良しな人、いっぱいいるでしょう?ほら、留三郎とか伊作とか」 そこでなんで俺や伊作の名前が出てくるんだ、と一瞬驚いたものの、下級生が喧嘩したのはくのいちの友人ではなく忍たまに友人であるという考えにたどり着き納得する。なるほど、忍たまのやつと喧嘩をして、叩いてしまったというわけか。下級生も「あぁ!」と明るい声で返事をしたものの、すぐに「でも…」としょぼくれた声色で続けた。なんだなんだと聞き耳をそのままたてる。 「食満先輩や善法寺先輩とはちがうじゃないですか…」 「あー、んー、まぁ、そうだね、そうだけど」 違う?!違うとはなにが違うんだ?!も返答には困っている様子みたいだが、一体どういうことなのだ。俺や伊作が、下級生が喧嘩した相手となにが違うというんだ。学年が違うのは当たり前だ、だがそんなことであればが言いよどむことはないだろう。性格が違うということも当たり前だ、これも返答にはさして困らないはずだ。ならばなんだ、なんだというんだ。そう俺がもんもんと考えている間には下級生を言いくるめたようで、の「頑張ってね」という励ます声と、下級生の「はい!先輩、ありがとうございました!」という明るい元気な声が聞こえる。 そのまま軽く走り去る音が聞こえて、下級生が声が届かないくらいまで遠くに行ったのを見届けたのであろうが、「留三郎」と俺の名前を呼ぶ。それには別段驚かず、おう、と俺は短い返事をした。仮にも忍術を学ぶ学園の最上級生だ、普段からあまり気配を悟られないようにはしているものの、ここは戦場ではないのだ、完全に気配を殺すということはしていない。なので、俺が彼女らの話を途中から聞いていたことくらいは分かっているはずだ。俺もそれを承知の上で、気配を完全に消すということはしないでいたのである。もし先ほどまでの話がや下級生にとって聞かれたくない話であるのなら、何かしらの行動が彼女にはあったはずであり、それがなかったということは俺が聞いてもいい話、あるいは俺にとってどうでもいい話なのだ。今回の場合はどうでもいい話、であったようだが。 「盗み聞きとは悪趣味だね」 「女子の泣き声が聞こえたら何事かと思うだろ、普通」 「ふうん…」 胡散臭そうに相槌を打ちながらは茂みの中から出てきた。さすが食満先輩はオトコマエですこと、と嫌味っぽい台詞も聞こえてきたのだが、ここは持ち前の理性でなんとか自身の感情を押しとどめる。大人になるんだ、俺。 「うちの後輩とでも喧嘩したのか?あの子」 「そうみたい。まぁ、下級生の頃はくのいちと忍たまの仲が悪いのはいつになっても同じってことよ」 「だな。俺らの学年も酷かったもんな」 「ほんと。伊作や小平太はともかく、仙蔵や留三郎ったらもうほんとむかついたわ」 「そっくりそのまま同じ言葉返すぞ」 いたずらを仕掛けては仕掛け返しての繰り返し、合同で授業を組むようになると腕が立つために組みやすいことは組みやすいのだが如何せん口と態度が悪すぎる。かと思えばいつの間にか伊作や小平太とは仲を深めており、さらには長次とは言葉少なくとも信頼関係を築いているようで、まだ幼かった俺はいろんな意味で爆発した。と一番関わっているのは俺のはずなのにどうして俺とが一番険悪なんだよ!と伊作がいないときに部屋で暴れていたことは黒歴史だ。ちなみにその暴動は伊作、そして別部屋の同期たちにもバレていたらしいのだが、今はその話は置いといて。まぁ大丈夫だろうね、と下級生が走り去った方向を向いてどこか晴れ晴れとした様子で呟いているに、実は先ほどから気になって仕方ない質問をぶつけることにした。 「さっきの、俺や伊作とは違うって、あれはどういうことなんだ?」 「えっ?!あ、あれねー…あー…あはは」 「なに笑ってごまかそうとしてやがる」 「ごまかしてないごまかしてない」 先ほどの晴れ晴れとした様子とは裏腹に、一瞬でぎくりと顔をこわばらせたに疑いのまなざしを向ける。は先ほどの俺の言葉を否定しつつ乾いた笑いを零しており、やがて「あー…」と再び言葉を濁しながら先ほどまで下級生と話していた茂みを見た。俺もそちらに視線を向けるが、その茂みからはなにも読み取れない。 「いやー、実はね…あの子が叩いた子っていうのが……」 「なんだよ」 「…うん。いや、俗に言うアレだよアレ。…想い人?らしくて」 「…おぉ」 「うん…まぁ、そういうわけですわ」 「…そうか」 俺はなんとも返すことができず、はこの話題は終了とでもいうように無理矢理話を締めくくった。つまりあれだ、は下級生に向かって叩いてしまった子と仲良くなるのなんて簡単だと言い放ったが、下級生は違うと。普通の男子ならともかく、好いている人にそんな素直に仲良くしてくださいと言えるか、と。多少解釈の仕方は違っているかもしれないがまぁこんなところだろう。しかしそれは裏を返せばは俺や伊作をそのような対象としては見ていないのだということが今の会話で見て取れた。伊作に関してはそれはむしろ歓喜することだ。が伊作を好きになり彼と添うようになったとしたら、伊作はまでもを不幸の道へと引きずりかねない。それではがあまりにもかわいそうだ。…と、カッコ良く言えたらいいのだが。 確かに彼女を哀れむ気持ちが大部分なのだが、残念ながらこの件に関しては俺のやましい気持ちがほんの少し入り込んでしまっていた。先ほど告げた黒歴史、あの当時はそもそもこの感情が芽生えていたのかどうかさえ分怪しいのだが、年が流れるにつれ自覚していたことであった。要するに、俺はのことを想っていた。先ほどのように偶然声が聞こえて立ち止まってしまったというのも、このような理由もあったからだった。 お互いどこか気まずそうに、俺は片手で不自然には見えないように口元を覆い、は髪の束の先を指でもてあそんでいる。もうこの頃には俺は当初の目的、用具倉庫に行って委員会の時の仕事を少なくしておくということはどうでもよくなっていた。委員会の後輩たち、すまない。 「あ、えっと、留三郎もよく相談とか受ける?下級生から」 「ん?あ、あぁ、そうだな。もよくあるのか、こういうこと」 「うん、まぁ、6年生だしね」 そうだな。そうだね。そこまでいって、会話終了。おい、どういうことだ、これまでにとここまで気まずい雰囲気になったことなんてないんだが。 俺がを気まずくさせているのだろうか、と手で口元を覆ったままちらりと斜め下の彼女を見やると、俺の視線に気付いたの視線とちょうどかちあった。俺はしまった、とすぐにぱっと視線を前に戻したのだが、気になってそろそろと今度はバレないように視線を斜め下に向けると、はこそばゆいとでもいうかのように口元をもぞもぞと動かしながら相変わらず束ねた髪の先をもてあそんでいる。 だが、次の瞬間、へらりと口元を緩めたしあわせそうな締りのない笑みを、俺は確かにこの瞳に写していた。 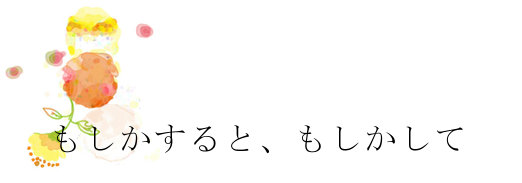 140106(まんまとrkrnにはまりました食満先輩に落ちました。最初はもちっとしんみり〜なお話書こうとしてたんだけどほのぼので終わっちゃった…まぁこれはこれでいいか。2014年初書きしかも初rkrnというはじめてだらけ。素材ははだしさんより。) |