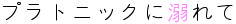
「さんて、正十字の生徒やないんです?」
「うん」
「普通の勉強は?」
「自宅で」
「よう、ひとりでできますね」
「家庭教師いるから」
「家庭教師?」
「近所のお兄さん」
祓魔塾に通い始めて数週間。制服姿が多い生徒の中、毎日私服で塾にくる彼女はいろんな意味で目立っていた。授業での発言以外は特に会話はなく、いつも塾生の誰よりも早く来ているくせに帰るのは一番遅い。休み時間は本を読んでいるか次の授業の予習をしているかのどちらかで、塾内の誰もが彼女、という人物は“そういうひと”なのだと思っていた。
例に漏れず、俺も初めは彼女に対して何の興味も抱かなかった。ちょっと変わった子がいるなというような認識だったのだが、とあることがきっかけでよく会話を仕掛けるようになったのだ。会話と言っても大抵俺が一方的に話しかけているだけなのだが、さんも対して嫌がっているわけではなさそうで。むしろ相手も俺との会話を楽しんでくれているのだと、そう思うのは自意識過剰なのかもしれないが。
「でもさん頭ええやん、高校行ってえんのにそれはずるいわぁ」
「志摩くんも頭いいじゃん」
「俺とはまた違った部類の頭ええ、やん?俺は記憶力ええだけ」
「…人はそれを“頭がいい”って言うんだよ」
さんは呆れたように言ったけれど、そこに嫌味っぽさは全くない。だから彼女との会話は好きだった。彼女には1を言えば3・4は伝わる。全てを言わなくても伝わるというのは、楽、というよりもむしろ心地が良くて不思議な安心感に似たようなものがあった。なのでやはりどうしても、他の同級生と会話をしていると彼等を子どもっぽく思ってしまうのだが、それは仕方のないことだと思う。それはきっと彼女も同じなのだろう。俺は彼女が無口な所以は、そこから来ているのではないかとも思っていた。
そして俺は、そんな彼女に知らず知らずのうちに惹かれていた。
「志摩くん、携帯」
「え?あ、気づかんかった」
チカチカと机の隅で光る携帯を手に取った。メールだ。受信ボックスを開くと、母親から『GWは帰ってくるん?』という簡潔なメールが1通。急速な返事を待っているようにしか見えないその内容に、眉根を寄せて頭の後ろをガシガシと掻いた。もうそんな時期なのか。
「…どうかした?」
「ゴールデンウィークの帰省、どないしようかと思ってん」
「あー、そっか。もうそんな時期か。早いねぇ」
俺としてはさんの意見を求めているつもりだったのだが、彼女はそんな俺の心を知ってか知らずかさらりと世間話のひとつとして流してしまった。シャーペンをくるくると回しながら祓魔塾の課題を解き進める彼女に、ひとつの質問を投げかけようとして、一瞬戸惑う。聞いてしまって、いいのか。俺と彼女はこの質問をするに足りる距離なのだろうか。
するとさんは俺の視線を感じたのか、問題集から顔を上げて俺の方を振り返った。そして「なに?」と告げる。ええい、言ってまえ。
「結葵さんは、ゴールデンウィークの予定とか、あるん?」
「予定?…特にないよ。帰省しないし。図書館行って勉強しようかなとは思ってるけど。それがなにか?」
「や、参考にさせてもらうわ。ありがとな」
「いーえ」
再び問題集に取りかかった彼女を横目に、母親には『ごめん、残るわ』というメールを素早く送って携帯を閉じた。そして携帯をカバンの中に放り投げ、ノートの上に落ちていたシャーペンを手に取る。そして俺も問題集の問題を3問ほど解き終わった時、さんがふいに尋ねてきた。
「…残る?」
「え?」
「ゴールデンウィーク。返事したんでしょ?」
「あ、おん。ゆっくりしたいし、勉強しなあかんし」
まるで取ってつけたような理由だな、と内心自分に苦笑を漏らしながらそう告げた。けれどそれもあながち嘘ではない。最終的には自分の意志で決めたことだ。さんが残るなら、という理由は、まぁ、ちょっとだけあるのだが。
「…ね、」
「ん?」
「よかったら、一緒に図書館で勉強する?迷惑じゃなかったら」
「…、お、おん、ええよ」
心の中でガッツポーズを取った。
back プラトニックに溺れて next
|