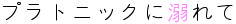
「え、志摩帰らへんの?」
「おん、残るわ」
「俺帰るって返事してもたんやけど…」
「土井だけ帰り、親に顔見せたれや」
同じ京都出身でルームメイトの土井は、唇を尖らせながら「志摩も帰ろうやー」と誘ってくる。今年16歳にもなろう男が女々しいんや、と一蹴すると土井は文句を垂れながらも1人で帰ることを承諾した。なんだかんだで親孝行な友人だ、彼の家庭は一人っ子であるし、なるべく顔を見せに帰ってやりたいのだろう。
「でもどうしたん?俺てっきり一緒に帰るんかと思ってたんやけど。予定でもできたんか?」
「予定なぁ…ま、そんなとこや」
「もしやさん絡み?」
「…お前、エスパーかなんかか?」
当たりやな、とニッと笑みを浮かべた土井はそのまま立ち上がると部屋に付いている冷蔵庫からアイスを取り出した。安い、フルーツの味がする、真ん中でポッキリ折るタイプのやつだ。土井はその紫色、すなわちブドウ味を取り出すとその場でポッキンと半分に折って半分を俺に寄こした。また先端が丸い方だ。なぜか土井はこっちのほうが食べやいすいからと、いつもこのタイプのアイスでは先端が細長い方を選ぶ。
それを口にくわえてシャクシャクとアイスを食べながら、俺は机の椅子に、土井はベットに腰かけた。
「エスパーもなにも、それしか理由思い当たらんもん」
「…言うなや。うちの親に」
「そこまで野暮やないわ、俺も」
「そーかい」
恥ずかしくて土井から目をそらしながら、半分くらい中身がなくなったビニールの容器をガジガジと甘噛みする。土井は足を組んでアイスを口にくわえながら、そんな俺のことをニヤニヤとした様子で見ていた。「ええなぁ春やな〜」とまるで俺の一番下の弟のように呟いた彼も、全くモテないというわけではないと思うのだが。
土井にさんとのことがばれたのはかなり早かった。そして俺のこの想いがばれるのも。それ以来少々の冷やかしはこうやってされるものの、なんだかんだ応援してくれているらしいので特に気にしていなかった。まぁ、他の誰かにばれるよりかは土井のほうがまだマシだと思う。俺との付き合いも短くはないので、そう長く隠せるとも思ってはいなかったし。そう思いながら、殻になったビニールの容器をすぐ傍のごみ箱に投げ入れた。
「で、どこ行くんや?結葵さんと、ゴールデンウィーク」
「…図書館」
「え?」
「やから、図書館やて。一緒に勉強するだけや」
「え?ほんま?」
「…ほんまや」
「…なぁ、健全なお付き合いすぎん?それって」
「黙れや土井」
俺はベットに腰かけている土井にひと蹴りいれてから、再び机に向かって椅子に座りなおした。ええやん、健全なお付き合いで。俺とさんはそれ以上でも以下でもないんや。そう思いながらも、やはり図書館という場所を提案してきたさんに、自分と彼女の距離は未だその程度なのだと感じずにはいられなかった。
back プラトニックに溺れて next
|