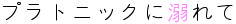
もちろん図書館内では飲食禁止だったので、ゴールデンウィーク中は昼食を取ってから12時に集合、ということになっていた。そしてそのままぶっ続けで6時まで勉強して、息抜きがてら公園でアイスを食べてから解散、という日々が続いていた。そしてさんと一緒に勉強をするようになってから初めて知った、彼女の一日の学習量。高校にも通わず自宅で勉強しているのだからかなりの量をこなしているのだろうとは思っていはいたのだが、まさかここまで勤勉家だったとは。しかも頭がいいから進みも早い。俺達が高校1年で習う課程をもう既に終えているらしい彼女は、市販されている教科書と問題集で一人で着々と一般教養の基礎を積んでいた。俺は高校の進度に合わせざるを得ないのでこればかりは仕方ないとはいえ、彼女に想いを寄せる身としては情けない。さんのほうが先に進んでいるなんて。しかも祓魔の勉強も俺と同等の知識を積んでいるらしく、それにはちょっとショックを受けた。致死節の暗記量には、大分自信があったというのに。
「さん、どこでそんな知識蓄えたん?近くに祓魔師のひととかおるん?」
いつもの如く図書館の帰り、公園でアイスを食べながら世間話のひとつとしてブランコに座っているさんに聞くと、彼女はきょとんとしてから「言ってなかったけ?」とアイスを食べる手をいったん止めた。
「うち、薬草屋やってるの。日本支部御用達の」
「し、支部御用達…?!」
「あと母のほうが祓魔師だった」
「だった…?…あ、ごめん、」
「気にしないでいいよ。他界したのもう随分前だし」
さんの過去形の口調に謝罪を告げると、それは当たっていたようでさんはけろりと母親が他界済みだという真実を述べた。しかしそこから話を続けようにも続けられず口を閉じていると、さんも溶けかかっているアイスに集中し始めたらしく口を閉ざす。そうか、母親が。
「あ、もしかして家の手伝いしとるから、学校行っとらんとか?」
「家のせいにするわけじゃないけど、まぁ、そうなるかな。べつに家でも学校の勉強はできるし」
「そやったん…あれ、じゃあ祓魔師になる気はあらへんの?」
「いや、なるよ」
「え?じゃあ薬草屋は?」
「そっちもやる」
「…大変なんやね、さん」
家業である薬草屋の勉強をして、高校での一般教養も積んで、祓魔師の勉強もして。随分前から努力家だとは知っていたものの、彼女がいかに勉強に対して真剣に取り組んでいるかはこの数日でありありと分かった。そんなにたくさんわらじを履いている上に、どれも手を抜くことができるものではない。頭の良し悪しはもちろん、精神力や体力もどれだけ必要なのだろうか。目指すものはただひとつ、祓魔師だけである俺には想像もつかないが、途方もなく大変なことなのだろう。
そう、感心と尊敬の念を抱いて返したのだが、その言葉を聞いたとたん彼女は眼を丸くしてどこか居心地悪そうに視線を泳がせた。それは気まずい、というよりむしろ恥ずかしがっているのだとなんとなく分かる。
「…ごめん」
「え、あ、俺なんかマズイこと言ってもた…?!」
「ち、違う。あの、…う、うれしくて。最初から、そんなふうに言ってくれたひと…いないから」
いつも、欲張りすぎだって、鼻で笑われる。から。そう、ぼそぼそと告げたさんに俺も片手で口元を覆いながら視線を彷徨わせた。なんや、これ。ゴールデンウィークでよく一緒にいるからか前よりは言葉を交わす回数も、その返事も以前に比べて充実していると感じていたのだが、まさかこんなことを言われるなんて。うれしいとか、言われた俺の方が、うれしいに決まってる。
そう思いながらも、ブランコにのったまま俯くさんの頭をぽんぽんと撫でた。
「俺は、さんのこと、すごいと思うで?どれにも一生懸命やし、めっちゃ頑張っとるやん」
「あ、ありがとう」
「どれも、叶うとええな」
うん、と聞こえた返事があまりにも嬉しそうで、恥ずかしそうで、結局その日はお互いにろくに顔を見ぬまま別れた。寮に帰ってもなお、日焼けのせいだけではない熱が頬には残っていた。
back プラトニックに溺れて next
|